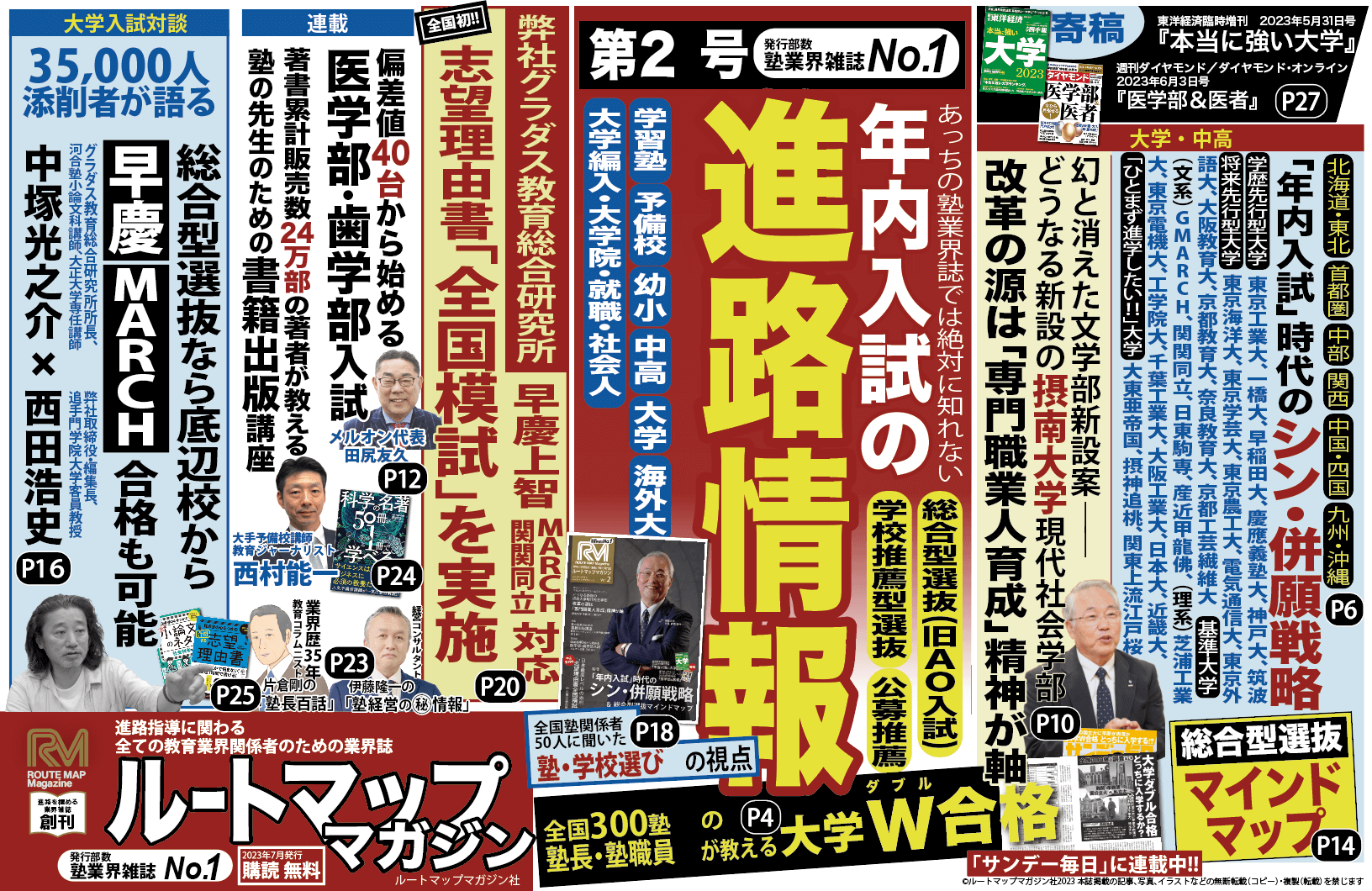国語の入試問題は現代文と古文の融合型が主流になりつつあり、古文対策に注目が集まっています。代々木ゼミナール、東進ハイスクールで現代文・古文のカリスマ講師として活躍し、『眠れないほどおもしろい蔦屋重三郎』などの著書で知られる板野博行氏に、今なぜ古文なのかを伺った。
最近、塾講師の間で、古文の勉強ニーズが高まっていると聞きますがなぜでしょうか。
板野文科省の人から非公式に聞いた話では、小学校での漢字や語彙の勉強を強化する動きがあるそうです。思考力を高めるためには語彙が必要だと文科省も気づいたのでしょう。その先には、英語教育、さらに先には国際人育成があるのだと思います。
しっかり日本語を学び、土台となる思考力を身に付けないと学力は上がりません。
また、いずれ国際人になったとしても、日本の文化を知らなければ外国人から日本について聞かれても何も答えられません。
そうした自国の文化を学ぼうとしたときに、避けて通れないのが古典です。
だからこそ、教育現場でも小学校のうちから百人一首や源氏物語、枕草子を学ぶ流れになっているのです。
入試では、先生の著書でも「現代文は点数が安定しないが、古文は点数が取りやすくコスパがいい。勉強しない手はない」と述べられています。
板野語学の「読む」「聞く」「書く」「話す」の4技能の中で、古文は「読み」しか必要ありません。よって労力は英語の4分の1。英語の勉強に4年かかるとしたら古文は1年でいいわけです。
多くの人は、古文の勉強を他の教科より後回しにしますが、逆です。最初に古文をしっかり学んで思考力の土台を作ってから、他の教科に手をつけたほうがいい。
早稲田大学やGMARCHで、現代文と古文を融合した複合問題が出題されました。現代文は点数が取りづらいので古文を強化して古文で確実に点を取るという戦略に今後は変わっていくと塾の先生方から聞きました。
板野複合問題の主旨は、従来の知識を問う問題から思考力を問う問題に移っているということだと思います。今後、流れは確実にそうなるでしょう。ですが、作問者も試行錯誤の段階で、問題の完成度はまだ低い印象です。
日本人の感性や日本文化は古文から学ぶべし
ところでネット上で「古文いらない論」が盛り上がっていますが、それをどう思われますか。
板野数学は論理的な思考力を鍛えるために必要だとすると、古文や漢文は感受性を育てるものだと思うのです。例えば「古池や 蛙飛び込む 水の音」という松尾芭蕉の俳句をすばらしいと感じる感性は日本人なら当たり前ですが、外国人には理解するのが難しい。そうした日本特有の感性が文化を形成しています。古文は自国の文化を理解するのに不可欠なのです。
古文を学び尽くした上で「不要だ」と考えたなら良いですが、学びもせずに「不要だ」と判断するのは浅い考えですね。
おっしゃる通りですね。
板野私は大学生の時に柿本人麻呂の、「あしびきの 山鳥(やまどり)の尾の しだり尾の 長々し夜をひとりかも寝む」を読んで泣いたことがあります。上の句の「あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の」には意味がない。最初の5・7・5には何も意味がなくて、本当に言いたいのは下の句の「長々し夜を ひとりかも寝む」。つまり、「長い夜、彼女がいなくて一人寂しく寝ている」なんですよ。この寂しさを際立たせるために最初の5・7・5がある。意味はないからこそ意味がある。そこに気づいた時には鳥肌が立ちました。これが古文のすごさなんです。こういう感性を大事にしてきた日本人ってすごい民族だなと思います。もしこれを口語訳したら「一人寝は寂しい」で終わり。感動も何もない。
西洋で著名なシェイクスピアは今から400年ほど前の人ですが、紫式部は千年前です。その彼女の作品が残っていて今でも理解できるのは、世界でも日本だけではないでしょうか。私たちはそうしたすばらしい国に生まれてきたのですから、古文を学ばないというのはあまりにももったいない。
最初に、「語彙は思考力」だと言いました。逆に言うと、語彙が失われると思考力も失われます。
ということは、古文を失ったら思考力もその部分が欠けてしまう。代わりに新しい何かが入ってくる可能性はありますし、それを否定するつもりはないのですが、せっかく良い伝統があるのなら、それを勉強しない手はないと思うのです。
小学校からの古文の暗記がおすすめ
古文は小学校から習ったほうが良いのでしょうか。
板野そうですね。例えば枕草子の冒頭や百人一首などをどんどん暗記すればいい。5、6、7歳は見たこと聞いたことをそのまま覚えられるゴールデンエイジです。意味なんか分からなくても、どんどん覚えるのが大事。意味はあとから分かってきます。
私も小学生のころ、『大学』という漢文で書かれた経書を意味は分からないまま何百回も読んでいました。大人になってから内容の素晴らしさが分かり、感動したことがあります。
板野小学生で『大学』とはすごいですね。子どもにはアメとムチではないですが、「十個覚えたらゲームをやっていいよ」みたいにして親子で楽しみながら暗記に挑戦するといいでしょう。百人一首なら1日2、3個ずつ覚えたら1カ月ちょっとで全部覚えられます。「何番を言ってみてよ」と言われて、言えたら褒めてもらえて。その小さな達成感がモチベーションになり得意につながっていく。自信がつくことで、古文以外の教科にも意欲的に取り組めるようになっていくでしょう。
最後に、先生の最新刊『古文単語革命99』について教えてください。
板野「入試カバー率99%」と書いていますが、小学生から読んでもいい。映像も付いているので、親子で楽しみながら学ぶのもおすすめです。語彙が増えて思考力や感性を育むのに最適ですので、ぜひご活用いただきたいですね。