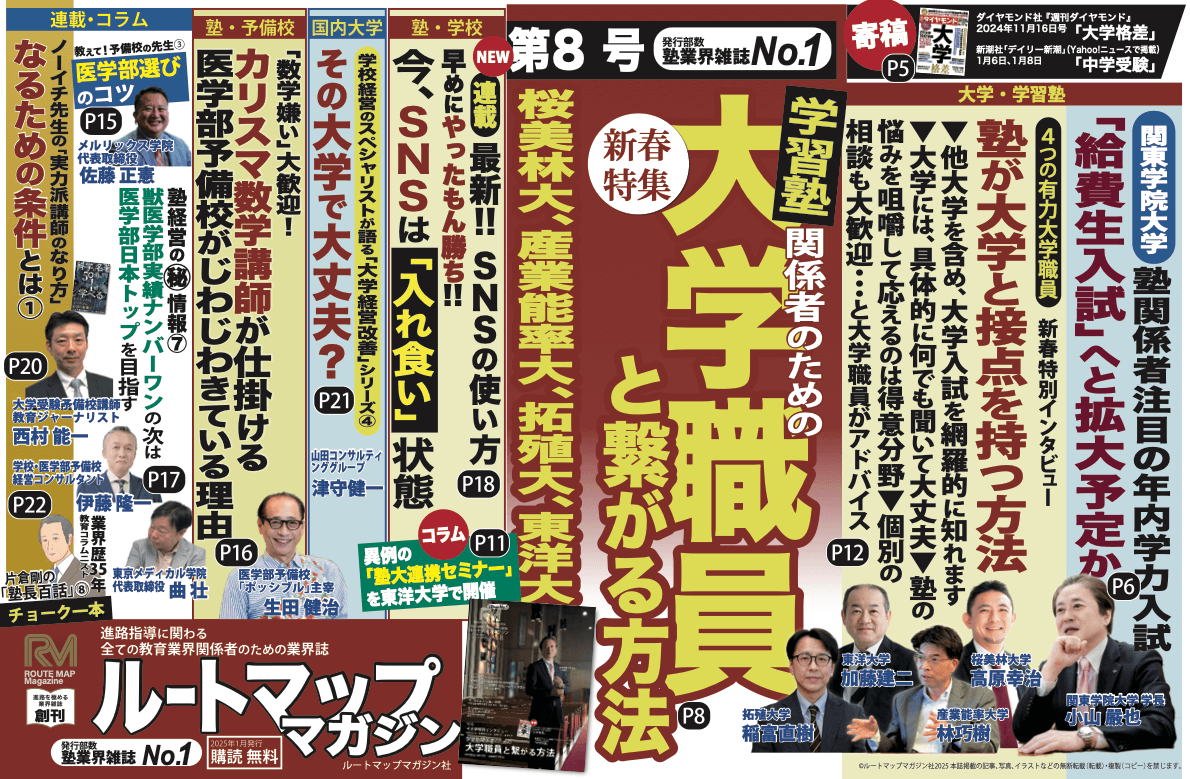5月中旬、南西諸島へ旅に出た。羽田から2時間半、奄美大島空港から車で南へ、古仁屋港からフェリーで20分。加計呂麻島へ渡る。島の中央呑之浦に、小説『死の棘』等で著名な「戦後作家島尾敏雄」の文学碑があり、すぐ近くの格納洞窟に自爆魚雷艇「震洋」のレプリカが置いてある。
敏雄は昭和18年9月九州大学をくりあげ卒業後、翌19年10月、隊員180名の震洋特攻隊隊長(海軍中尉)としてこの地に着任した。「震洋」は全長25メートルのベニア板の小艇で、船員1名、船先に250キロの爆薬をつみ込んで米国戦艦に体当りする自殺艇だ。成功の確率は相当低い。翌20年8月13日、出撃命令は下ったが、発信待機のまま、そのまま終戦の報告を受ける(小説『魚雷艇学生』『出孤島記』などに詳しい)。
レプリカ前の海岸に立ち、周りを見回す。対岸は南洋植物が自生する小高い丘で、360度人口の建造物は見えず、コバルトブルーの海は湖のような静けさにある。この夢幻的な美しさの中で、島雄隊長の心中を想像した。
なぜ小説を学ぶのか。多様なもののとらえ方や考え方を学習する上で小説を題材にしたい、と多くの教員、塾長は杓子定規に言う。しかしそれ以前に、小説を読むという営為は、想像力(共有感覚といってもいい)を喚起、育成するためだ、と著者は考えている。例えばこの特攻隊長として従軍した作者が、死を前提とする極限状態に、どのように生と死のおりあいをつけたのか。予備学生からたった2年で海軍中尉となり、特攻隊を志願するとはどういう心の変化だったのか。また「終戦を知って、生き延びようと腐心する私を支える強い論理を見つけ出すことができない」と作者は書くが、自分がその場にいたら、何をどう感じるのか。このまったく理不尽な状況は、全て想像力に委ねるしかないのだ。
2022年度の高校1年生の国語の教科書は「現代の国語」と「言語文化」に分けられた。前者が評論文など論理的な文章や実用的な文章に対し、後者は小説や随筆など文学作品や古典を扱うことになっている。だが最近、「現代の国語」に小説を掲載する例が増えているという。「言語文化」で古典を教える時間が増え、小説を読む時間が減少、必然的に「現代の国語」の小説が増えたからだ。
国語教育はどこへ向かうのか。例えば、80年前何があったのか。登場人物の複雑な意識の変化を私たちはいかに読み解くか。小説を読み文学作品に触れること、それが大きな未来への力になる。