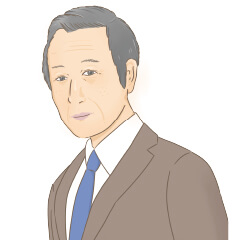三者面談や進路相談で明らかになるが、どこの塾にも、将来自分が何をやりたいか、何を学びたいか(学部選び)悩んでいる塾生がいる。そんな塾生に、塾長である貴方はどんな助言をなさるか。僭越だがたとえばその選択肢として、リベラルアーツをとり入れている高校のコースや、大学学部も考えてみてはいかがだろうか。人生は長い。リベラルアーツで世界の知見に触れ、その中から自分にあう将来の道すじが必ず見つかると思うのだ。
リベラルアーツを語るとき、文化人類学者の上田紀行氏(元東京工業大≲現東京科学大≳副学長、現東海学園大特命副学長)をはずせない。氏は2016年に東工大でリベラルアーツ研究教育院を立ちあげた。氏のHPでリベラルアーツとは何か、詳細に解説している。社会の色々な問題に対処するため、はば広い「教養」をもっている人が必要とされているのが現代で、自分を多様な世界へととき放ち、よりよい自分、よりよい世界へと導く入口となる。専門教育を受けてきた人が「役に立つ」とは限らない。その本来の言義は人間を自由にするわざ、人間が自由になるわざという意味だ。
この考えは他大学にも多大な影響を与える。例えばお茶の水女子大では、従来の教養教育を改革、学術知と実践知を兼ねそなえた女性が、21世紀に羽ばたくことを目標として、現代社会が直面する問題を発見し、解決する能力を鍛える教育をめざしている。ほかいくつかの大学は、国際(現代)教養学部という名称で、学際的な横断型のアプローチを試みている。
そしてこの流れは高校へも波及した。筆者は昨年末、塾関係者数名と2つの中高一貫校を見学した。一つは埼玉県にある「さいたま市立大宮国際中等教育学校」。2019年創立のこの学校では、後期課程(高1から高3にあたる)で3つのコースがあり、その一つが文系・理系の区分なく幅広く深い知識を得る、リベラルアーツコースだ。
またもう一校は東京都東久留米市にある著名な私学、自由学園中等部・高等部だ。創立百年を超え、「座学と経験で深まる教科の学び」「生きることそのものを実践する学び」「教科と年齢の枠を超える学び」を学びの柱としている。同校は広大なキャンパスに種類豊富な植生・本格的な畑、養魚池、養豚所などをつくり、生徒自ら食事づくりや野菜の育成、植林地や農場の活動などで、限りある命の大切さを学んでいる。自ら生産者として社会の構造を学ぶ、これこそリベラルアーツの学び、と言えると思う。