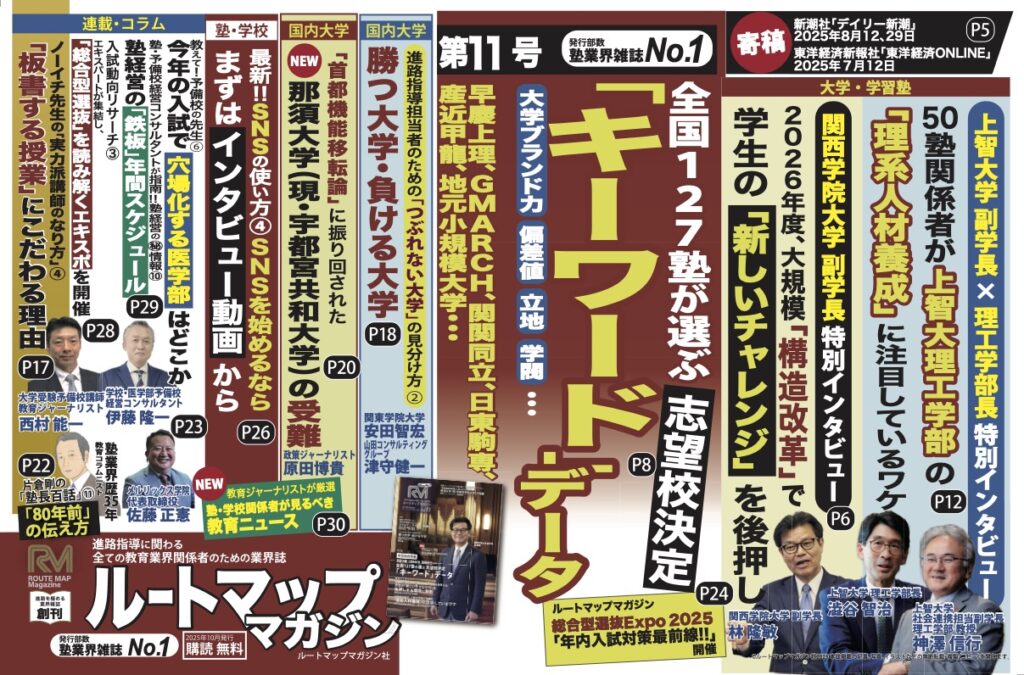池袋駅東口から徒歩3分。近年の再開発で注目の南池袋公園そば、13階建て新築免震ビル最上階に今夏、医学部予備校が開校する。
筆者は、これまで40以上の医学部予備校の経営に携わってきたが、ゼロからの立ち上げに関わるのは今回が初だ。“
その今までの「集大成」と言えるサービス・経営体制を整えた。
同業の関係者からは「これは医学部予備校のファーストクラスだ」との評価も多数いただいている。
早速本稿では、その一端を紹介しよう。
少人数、完全個室、AI、デジタル化がポイント
ゼロから立ち上げに関わったことで実現が可能になった大きな差別化ポイントをご紹介しよう。
まず、生徒数を30人に絞り、完全個室の自習環境を用意したことだ。
従来型の医学部予備校は、個別学習空間はあっても、周りの音に悩まされて気が散るなどの課題を抱えている。空間設計から私が関わることで、生徒が徹底的に学習に集中することが可能になった。
少人数にこだわる理由はもう一つある。一つのオフィスで、全てのスタッフが生徒のケアを丁寧に行える限界が30人だからだ。
それだけではない。首都圏の保護者層は、デジタルを活用し、効率的に最大限の学びを実現した。
それを可能にしたのが、「AIコーチングシステム」だ。これにより、データを利用した生徒のメンタルサポートや、学習進捗に応じた個別指導プランの提案まで行える。
例えば、試験結果を入力することでAIは生徒一人ひとりに適した学習計画を立案。その進捗は専用アプリで管理され、スタッフがチェックするデイリーコーチングと、チューターが行うウィークリーコーチングに活用される。
さらに、教材のデジタル化も積極的に行う。
デジタル教材を使い、それをAIと連携させることで出題選定や進捗管理の効率を格段に向上が期待できる。
前述のコーチングの際も、データを基に、生徒が暗記した内容の口頭試問を行い、知識の定着化をしっかり図れるようになる。
一方、そもそも入試は紙ベースで行われるので、デジタル教材は塾・予備校と相性が悪いと考える関係者も多い。
確かに、思考力を鍛えるには従来の紙テキストが効果的と言えるだろう。
当予備校でも、紙とデジタルの教材の融合、そしてスタッフによる人的サポートの融合により、効率的な学びとサポートを大幅に高める事ができるようになった。
このような、「デジタルとアナログの融合」は、令和の新しい受験勉強の形といえよう。
最先端の取り組みを一般の学習塾に展開も
さて、医学部予備校業界は、一時期よりも勢いが落ちたとはいえ、今後も堅調な需要が見込める。
医学部受験コースの全国の学習塾や高校への導入もこれから進んでいくだろう。
鹿島学園など、すでに通信制高校と提携している医学部予備校の事例も出ている。
これまでの医学部予備校は、「個人の学習進度や理解度に合ったカリキュラムを組むことが難しい」「学費が高額」「メンタルケアが不十分」「都心と地方の教育格差」といった問題点を抱えていた。
それが、今回のようなデジタルを活用した効率化が進めば、生徒一人あたりの単価を下げ、それら教育格差を解消し、低単価で高品質なサービスを提供することも可能になる。
将来的には、こうした医学部予備校のデジタルのノウハウを、ウェブを通じて全国の学習塾に導入できるようになれば、業界的にもメリットが大きいと言えるだろう。