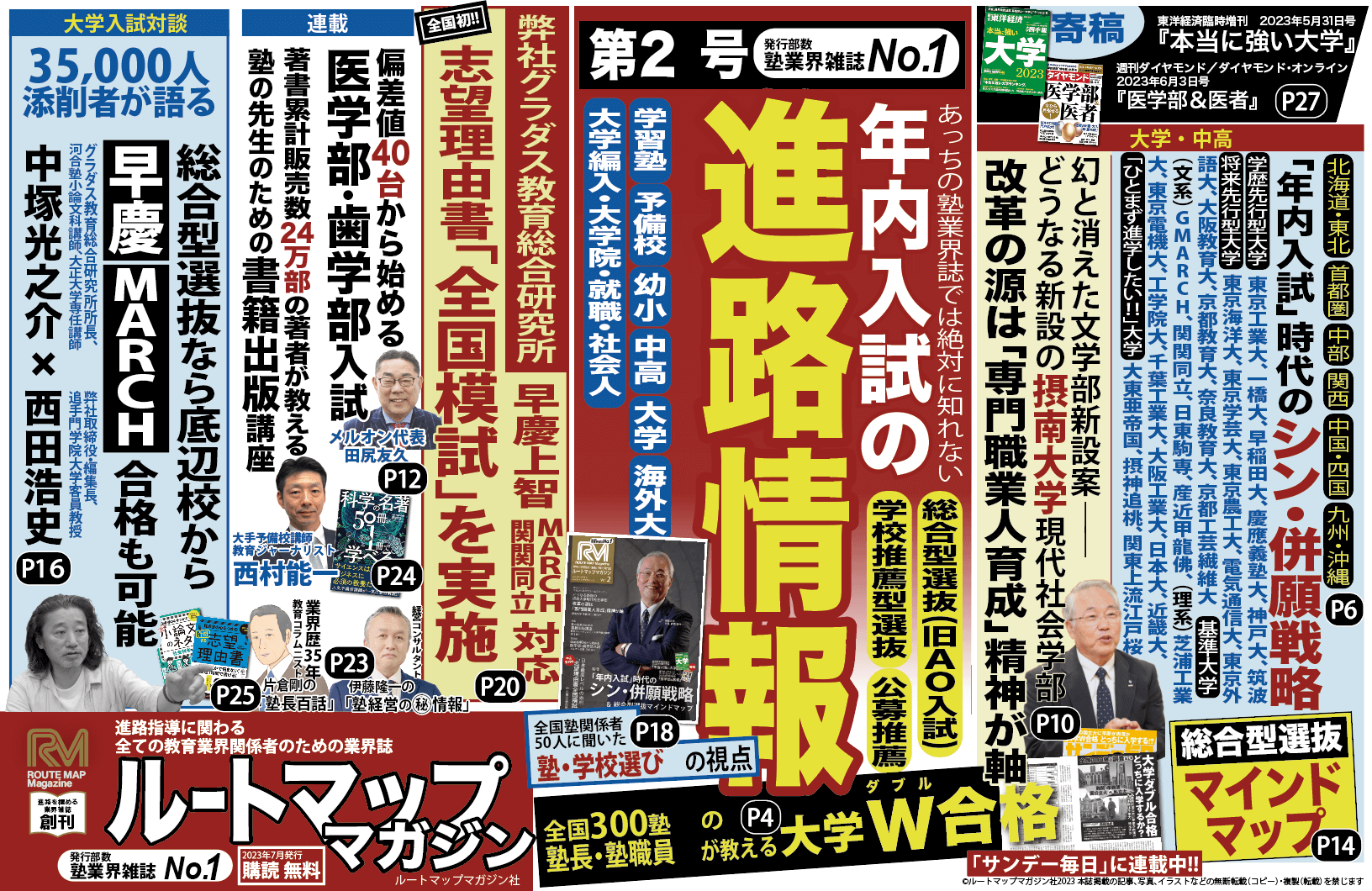国公立大学医学部に合格すれば、一般的には辞退はせずに「最優先」で入学する、それが当たり前と考える人が多いのではないでしょうか。
実はそうとはいえない、というお話をしましょう。
メルリックス学院が調査した、2024年度入試の国公立大学医学部の追加合格者数は、福島県立医科大学、横浜市立大学で各4名、山梨大学19名、信州大学6名、島根大学、高知大学で各2名、岡山大学、徳島大学、香川大学、鹿児島大学、琉球大学で各1名でした。
なんと、過去の22年度入試では、東大、京大に次ぎ偏差値が高い東京医科歯科大学(現・東京科学大学)で14名の追加合格者が出た事例もあります。
この追加合格者数というのは、いわゆる、入学辞退者数とみることができます。
思ったより高いと皆さん思ったはずです。
入学辞退は、「東高西低」
さて、前述した入学辞退者数では、「東高西低」です。
これは、大学の数にヒントがあります。
まず、国公立大学を東日本と西日本に分けた場合(信越を東日本、浜松医科大学は西日本でカウント)、16対34(東:西)となります。
一方、私立大学医学部(防衛医科大学校は除く)は20対11(東対西)です。東日本は私立、西日本は国公立色が濃い土地柄といえます。
この傾向は私立大学医学部の入試問題を見ても顕著です。東日本の私立大医学部の問題はマーク式もしくは解答記入型で短時間解答が求められる形式が多い傾向です。
一方、西日本は記述型が主です。さらに、解答時間も東日本の大学より多めで、記述問題を多く取り入れています。この理由は、国公立大学と併願する受験生に合わせているからです。
このように、入試問題一つをとっても西と東の医学部カラーの違いが鮮明に出ているといえます。
さて、首都圏の受験生は東京都内の大学を志望するケースも多いでしょう。
この場合、たとえ国公立大学医学部に合格しても、地方である場合、都内の有名私大を選択するケースも珍しくありません。
科学大vs慶應では?
例えば、東京科学大学と慶應義塾大学両方に合格した場合、OB輩出数、関連病院の数などから後者を選択することも珍しくありません。
さらに、地方国公立大学と私立御三家なら、後者を選択することもあり得ます。
加えて山梨大医学部の場合、後期入試の合格発表の時期が遅いので(例年、3月20日過ぎ)、有名私大の入学手続きや下宿先の手配がすでに完了していることも珍しくありません。この場合も辞退者数が多くなります。
一方、山梨大と同様に後期試験の定員が多い奈良県立医科大学からはほとんど辞退者が出ないのを見ても、東と西で医学部に関する考え方の違いが出て興味深いといえます。
最後に、ここまで入学辞退者数を見てきましたが、「潜在的辞退者数」も重要なポイントです。
まず、国公立大学の場合、第一段階選抜後の志願者数と実際の受験者数に大きな乖離があることも多いです。
これは、入試難度が低くなればなるほど顕著で、地方国公立大学だと30~40名程度の差になることもあります。
この数字の中には、上位大学を狙って浪人する数も含まれます。
さらには、メルリックス学院でも、有名私立大学医学部に正規合格して、国公立大学医学部の受験を辞退する層も毎年一定数出ています。
いずれにせよ、今後、国公立、私立という枠組みに関係なく、受験生は、より都市部の大学を志望する割合が増えてくるといえます。その点を私は注視しています。